2021年度愛知県芸術劇場レビュー講座課題
「やっぱり、どう足掻いても救われないのか」
勅使河原三郎版『羅生門』は勅使河原氏が振付、照明、美術、衣装デザイン、音楽構成を担当し、芥川龍之介作品の『羅生門』を下敷きに作成したダンス作品である。主な出演は勅使河原氏、佐東利穂子、アレクサンドル リアブコの3人で、勅使河原氏が下人、佐東氏が老婆の役という区分けは一応あるものの、作品には「何者でもない役」というものがあるようで、3人が交代でそれを演じるため役分けは曖昧である。
空襲警報のようなけたたましい音響とともに始まった序盤は芥川龍之介の『羅生門』の朗読に合わせてダンスの振りが発動され、芥川版『羅生門』に完全にリンクするかのように思えた。しかし朗読の省略される部分もあり、例えば下人が羅生門の楼を登っているはずのシーンでは笙の音に合わせてくるくるとしたつむじ風のような動きが繰り返される穏やかなダンスが踊られ、羅生門の時代―文治地震、大火、辻風で荒廃した京都にそぐわない雰囲気であった。
朗読の終わり-下人と老婆の話が終わった段階で本作品が芥川版『羅生門』を完全に下敷きにするという予想がいい意味で完全に裏切られていることに気づく。最後の一文「下人の行方は誰も知らない」という朗読が語られがらりと雰囲気を変える音楽、照明、そして-ダンス。2人の動きのリンクした激しいダンスに、笙の音に合わせた穏やかなダンス、暗い影の投影された舞台で暗闇の中から激しく絡みついてくる腕-急激に緩急の激しくなる振付に作品は急展開を見せる。それは芥川版『羅生門』に書かれなかった下人の決して平坦ではなかった生の足掻きを見せつけられているのか。「下人の行方は誰も知らない」のだから舞台に上がって踊っているキャラクターが説明されない分、その足掻きは当時の京都を生きるあらゆる貧困層の生の足掻きと捉えてもいいのかもしれない。頻用されていた手を絡めて捻ってという動きは苦悶の表現にしか見えなかった。
作中に笙の音の中で踊るシーンは全部で3回あるが、1回目、2回目のシーンはとても穏やかで生というより死後の救いのようなものを感じた。最終シーンの直前に舞台がぱっと照らされて光の中から人ならざる存在のようなものが出てくるシーンもそうだ。災害やそれに伴う貧困、飢饉で死ぬということが救いなのかは分からないが、おだやかな動きや照明を見ているとまるで苦悶の中に差し込む一条の光のように感じられた。それを一転させるのが最後のおどろおどろしいドットの照明の投影されるシーンと3回目の笙ーつむじ風のような動きを反復しようとしてできない、硬く緊張した身体を見せつけられるシーンだ。美しい笙の中で穏やかなダンスが繰り返されるはずなのに体が動かない、ぱっと舞台が明るくなるシーンの直後に投影される暗い影。それはまるで、救いがすぐそこにあるのにどう足掻いてもそこに辿り着けない人間の姿を描いているように思えた。
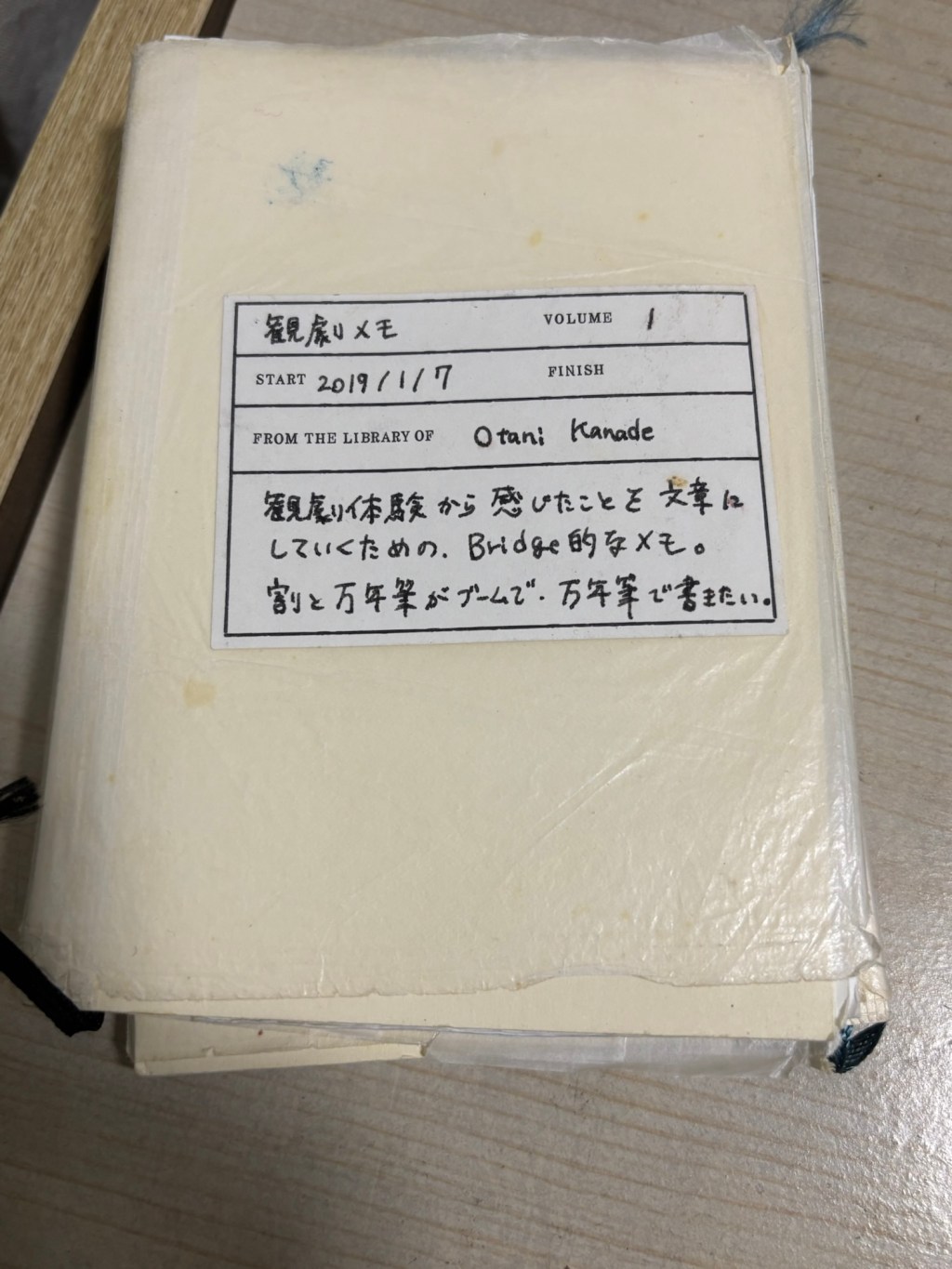
コメントを残す